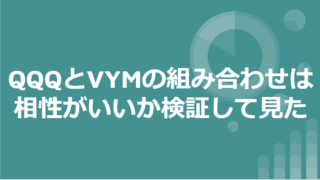2025年9月19日、ついに前任者の黒田総裁が残した負の遺産である「日銀が買ったETF・REIT」を売却すると植田総裁が発表しました。
植田総裁を批判する人もいますが、前任の黒田のおっさんが無茶苦茶にした後で、よく頑張ってくれていると私は思いますよ。
ただ、このETF・REITの売却発表後に高騰していた日経平均はマイナスまで株価は下落しました。
パニック売りもあるでしょうし、短期的に見て仕方ないことだと思います。
しかし、今まで日本株を底上げしてきた日銀の日本株の購入…これから、日本株はどうなるのか?
下手のアナリストよりも的を得たコメントをしてくれるAIさんに聞いて見ました↓↓
日銀が保有するETFとリートの売却は、日本株市場に短期的な動揺をもたらす一方で、中長期的にはその影響は限定的、あるいはポジティブな側面もあると見ています。忖度なく、その理由を以下に述べます。
短期的な影響:市場の動揺と需給の悪化懸念
日銀が売却を発表した直後、日本株市場は一時的に大きく下落しました。これは主に以下の2つの要因によるものです。
- 需給悪化への懸念: 日銀は日本株市場の主要な買い手でした。その巨額の買い手が売却に回ることで、市場に出回る株式の量が増え、需給バランスが崩れて株価下落圧力につながるのではないか、という懸念が広がりました。日銀が保有するETFは、日本株全体の時価総額の約7%に相当するとも言われており、その規模の大きさが投資家の不安を煽りました。
- 不確実性の増大: これまで誰も経験したことのない、中央銀行による大規模な保有資産売却という事態に対し、投資家は先行きが見通せないため、ひとまずリスク回避のために株式を売却する動きが強まりました。
中長期的な影響:限定的、あるいはポジティブな側面
短期的な動揺があった一方で、中長期的には以下の理由から、その影響は限定的、あるいは日本株市場にとってポジティブに作用する可能性もあります。
- 段階的な売却方針: 日銀は、市場に大きな影響を与えないよう、時間をかけて段階的に売却を進める方針を明らかにしています。年間の売却ペースは簿価ベースで約3,300億円と、日銀が保有するETFの総額と比較して非常に緩やかなペースです。このペースであれば、市場が吸収できる範囲内と見られています。
- 市場の自律性回復: これまでの日銀のETF買い入れは、株価下支え効果がある一方で、市場の価格形成機能を歪めているという批判もありました。日銀が買い手から退場することで、市場本来の需給に基づく健全な価格形成が促され、長期的な市場の自律性や透明性が向上する可能性があります。
- 金融引き締めとしての効果: ETF売却は、実質的な金融引き締めの一環と見なせます。これは、日本経済がデフレから脱却し、物価が安定的に上昇する段階に入ったことの証左とも捉えられます。健全な経済成長の証拠として、海外投資家からの日本株への評価が高まる可能性も考えられます。
まとめ
結論として、日銀のETFおよびリート売却は、短期的な市場のボラティリティを高める要因となり、特に発表直後は大きな株価下落をもたらしました。しかし、日銀が市場への影響を最小限に抑えるよう、緩やかなペースでの売却を決定したこと、そして市場の自律性回復という長期的なメリットを考慮すると、中長期的な日本株市場へのネガティブな影響は限定的であると分析します。むしろ、日銀の異常な買い入れが終わり、市場が正常化することで、投資家からの信頼を再び獲得し、日本株市場がより健全な発展を遂げるきっかけとなる可能性すらあると言えます。
↑↑ここまでがAIさんのコメント。
最新情報でも対応できるようになって…AIの進化ヤバすぎる問題(笑)
ちなんに植田総裁は、「売却には100年ぐらいの期間が必要」と発言しています。
株式市場に影響がでないように少しずつ売却していくそうです。
前任の肩書だけのおっさんと違って、きちんと考えられた政策ですね。
「日銀の日本株の大量保有」…異常ですからね。
短期的に見れば、相場が荒れる材料ではありますが、負の遺産を持ち続ける方がリスクが大きいです。
先延ばしするのは日本人の悪い癖です。
今回の件で、少しずつでもいいので、日本の金融が良い方向に向かってくれればいいと思います。
1日1回 応援ポチッとして頂けると毎日更新する励みになります⇩⇩
にほんブログ村
以上で今回の記事を終わります。
今回の記事があなたのなにかに役に立てれば幸いです。
オススメ書籍